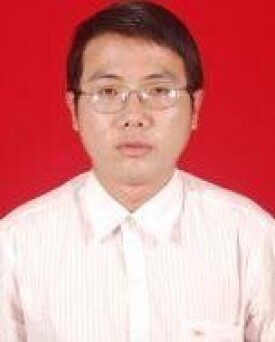宇野治
宇野治
宇野治(うのおさむ、舊姓:小林、1947年9月2日 - 黨內では志帥會所屬。北海道常呂郡留辺蘂町出身)日本自由民主黨人,眾議院議員,自由民主黨幹事會副幹事長。時任日本內閣府政務官。
1966年3月 ‐ 立教高等學校(現・立教新座高等學校)卒業。同級生に小川敏夫、本田明彥。
1970年3月 ‐ 立教大學経済學部経営學科卒業
1970年4月 ‐ 東京芝浦電気株式會社入社
1975年10月 ‐ 宇野宗佑の娘と結婚し宇野に改姓
1987年11月 ‐ 東芝を退社し外務大臣秘書官就任(外相は宇野宗佑)
1989年6月 ‐ 內閣総理大臣私設秘書(首相は宇野宗佑)
1991年4月 ‐ 滋賀県議會議員選挙當選(3期)
2003年11月 ‐ 第43回眾議院議員総選挙にて滋賀県第3區から出馬するが、小選挙區では民主黨の三日月大造に及ばず、比例代表當選(近畿ブロック)。
2005年9月 ‐ 第44回眾議院議員総選挙にて前回同様に滋賀3區では三日月に及ばず(ただし266票差)、比例當選。
2007年8月 ‐ 安倍改造內閣にて外務大臣政務官就任
2007年9月 - 福田康夫內閣にて引き続き外務大臣政務官再任
2008年8月 ‐ 福田康夫改造內閣において內閣府大臣政務官に就任。
中新網東京5月21日電(記者 朱沿華 關妍)二十一日上午十二時十分,日本外務大臣政務官宇野治弔唁四川大地震中的遇難者,並向中國駐日本大使崔天凱表示,如有需要當天早些時候由四川回到日本的國際緊急救援隊願二次赴華協助中國的震后救援工作。
在對地震遇難者進行弔唁之後,宇野治與崔天凱進行了簡短的會談。崔天凱大使首先代表中國政府和中國人民對日本在極短的時間準備了大量災區急需的物資和救援隊伍送抵地震災區表示衷心的感謝。他強調說日本外務省在之中起了巨大的作用,對此他非常感謝外務省的工作人員。
在談到日本政府和人民在中國受災后給予中國各方面迅速及時的援助時,崔天凱大使表示:“日方的援助是站在全面推進中日戰略互惠關係這個起點上面的,反映出中國國家主席胡錦濤早前對日本進行國事訪問在日本國內所產生的積極影響。此次地震災害是對中日戰略互惠關係很好的檢驗,也確實讓我們看到了中日戰略互惠關係的重要作用。我希望在進一步做好抗震救災工作的同時,中日兩國能夠藉此勢頭將兩國關係,以及兩國人民之間的感情推進到一個新的高度。”
宇野治政務官非常贊同崔天凱大使的觀點,稱日本民眾在媒體上看到中國民眾對日本國際緊急援助隊高度讚揚的報道后非常高興,希望中日兩國關係越來越好。他表示,日本外務省正在全國範圍內緊急徵集中國地震災區急需的帳篷、藥品等物資,準備就緒之後立即運往災區。另外,在抗震救災工作重心逐步轉向衛生防疫的新階段,日本計劃在第一批醫療隊之後再派出醫療專家團趕赴災區。同時,今天早上回國的國際緊急救援隊也希望外務省向中國方面轉達,如果四川地區再發生泥石流等次生災害,他們願意再次赴災區救災。
歴史と問題點
消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降である。成長の背景には、バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したこと、自動契約機の導入(1993年以降)、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁(1995年)されたことなどがあった。これらの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。その結果、駅前の雑居ビルの狹い店鋪で擔當者と向き合って融資を申し込むといった舊來の形だけではなく、郊外の國道沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増加した。また、「女性専用ダイヤル」と稱して、女性スタッフとの電話で振り込むという、実際には傍らに男性がいても「女性対女性」をうたい、女性が安心して融資を受けられると錯覚する環境を作る會社も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開(上場)する會社も現れた。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。
そのような中で2000年前後からは全情連(全國信用情報センター連合會)加盟の情報センター、CIC、全國銀行個人情報センターの個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、與信の厳格化が図られた。これによって大手6社などでは契約者の屬性が向上し経営自體は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挾まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒產、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(會社更生法が適用され更生計畫が認可されると、更生計畫に入っているものを除いた會社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払金返還請求に大きな影響がある)。本來、信用情報の目的は貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって多重債務者の発生を減少させることにある。この點につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるが、この行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその會員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。したがってこの指摘は目的外使用に民事上の責任追及しかなされないことの問題を指摘したものということができる。また、個人情報保護法が適用される信用情報に関しては同法違反となる可能性もある。
なお、この頃「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による與信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解もある。他方、消費者金融業界は、原因は2000年の出資法改正による上限金利の40.004%から29.2%への引き下げによる中小零細業者の撤退・倒產にあるとしており、業者の淘汰の原因を信用情報の交流に求めるか法改正に求めるかの點において上記の見解と異なる。また、この2つの見解と異なった視點から、この時期のヤミ金被害急増の原因は不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負擔の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、攜帯電話の普及などにあるとする見解もある。2003年にヤミ金対策を主目的に貸金業規製法が改正されたと同時に、出資法の上限金利の引き下げが論じられたが実現しなかった。
近年、大手の消費者金融會社は、銀行と提攜しローン(個人向けの銀行ローン)保證業務に乗り出したり、また、メガバンク(持株會社を含む)の資本參加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる數々の問題、高金利、押し貸し(貸し込み競爭)、「武富士」創業者の元會長が関與した電話盜聴事件などの社會問題が依然として解決されていないと言える[3]。「借りた人間が悪い」とする意見もあるが、「大手消費者金融業者の営利広告の影響等により高金利の借入に対する抵抗が減少した」などの指摘や、(連帯)保證人以外の家族等法律上弁済の義務を負わない人間が返済にかかわっている例が多くあるなど「借りた人間が悪い」という決め付けだけでは済まない問題も発生している。
分母である自殺者全體の増加もあるが、利用者の自殺の増加が指摘されており、返済を続けても、完済が困難である狀態は「サラ金地獄」とも呼ばれる。警察庁の統計によると、多重債務などの経済苦が原因とみられる自殺者は2006年に約8000人とされている[4]。また、2005年における大手5社利用者の自殺は判明しているだけで3649件であった[5][6]。20歳以上の死亡者に占める自殺者の割合は2,8%(人口動態調査05年、厚生労働省)であるのに対して、金融庁などによると、大手5社利用者の死因判明分に占める自殺率は25,5%であった[7]。
2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団體生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出た。本人が契約自體を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われる。2005年に大手5社が支払いを受けた件數は延べ3萬9880件であり、自殺によるものは判明しているだけで3649件にであった[8]。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不當利得の返還を遺族が消費者金融に求められる狀態)であっても保険金は消費者金融に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられない。この保険が存在せず、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した殘債務を利息無しで一括・分割返済(3 - 5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任する。
一般に、消費者金融は利息制限法を超える金利での貸付の場合、みなし弁済の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて回収を急ぐことがある。全額の回収を容易、確実にするために、連帯保證人付きのローン・不動產擔保ローンでの借り換え、公正證書の作成等の手段を用いる場合もある[9]。過払いが生じている法律上支払義務のない債務者に対して、強引な取立てを行うことも常態である。過払いが生じている場合は訴訟による回収が困難であるが、被告が裁判を欠席、答弁書を提出しない場合、また訴訟以外では支払督促に対して督促異議の申立てをせず放置した場合等、例外がある。
厳しい取り立ては違法な手段(脅迫罪・強要罪・住居侵入罪・不退去罪・業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することもある)を伴うことも多く、當事者・関系者に多大な苦痛を與える點で問題があるが、専門家(弁護士・認定司法書士等)の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21條6項の規定により貸金業者が債務者に接觸することは原則としてできなくなる。
なお、最近では店舗や無人契約機での申し込みは減少し、インターネット経由で申し込みをして審査を一通り終わらせ、最寄の無人契約機でキャッシングカードを受け取りに行くというケースが増加している。
また、最近さかんに宣伝されている「おまとめローン」には次のような問題がある。
まとめる前に任意整理などを行えばできたかもしれない「引きなおしによる債務の減額」ができなくなる。したがって実質的に債務が増えてしまうことがある。
特に過払いの場合は「もともと払う必要のなかった債務」をあらためて背負うことになる。
上記の問題を考慮して、過払い金が返還される可能性について注意を喚起する但し書きをCM、広告などに付している場合がある
近年の金融庁による指導など
2006年4月:クレジットカード會社の一つである「オーエムシーカード」の子會社であるアルファオーエムシーに対し、金融庁は4月24日から5月18日までの25日間、債権回収をする管理センターの業務停止命令(弁済の受領などを除く)を出した。擔當者3人が昨年11月、3日間にわたり合計6回、債務者の妻に電話をかけ、借金の一括返済などを迫ったことなど違法行為が繰り返されていたとして貸金業規製法に違反する過剰な取り立て行為に當たると判斷した。
2006年4月14日:「アイフル」に対し、融資や取り立てを巡る違法行為が繰り返されていたとして、全店に対し5月8日から3~25日間の新たな顧客の勧誘、融資などに関する業務停止命令が金融庁より出された。
2006年7月27日:「アエル」(ローンスターグループ)は関東財務局から、貸金業規正法違反により約250ヶ所ある支店や事務所で2006年8月21日から3~26日間の全店業務停止命令を受けた。
2006年8月23日:「アコム」に対しおこなわれた金融庁の定例検査の際、朝日新聞により「業務停止命令を前提とした異例の再検査」との報道がなされたが、その後なんら処分は科されていない。
2006年10月20日:「レイク」は、債務者の依頼を見落とし勤務先に督促の電話をかけたとして、金融庁から11月13日から11月17日までの5日間業務停止命令(東京と大阪の電話サービスセンターが対象)を受けた。
2007年4月4日:三和ファイナンスに対し、違法な取り立て行為などを行ったとして、全店舗での業務停止命令処分発動。組織的な違法行為があったと判斷され、4月23日から、最長で6月27日までの長期となった。
2008年7月4日:貸金業者が2008年4月21日付けの夕刊紙やスポーツ紙に掲載した広告について、金融庁などが調査を実施、不適切な內容とされた148業者に対して行政対応がされた。→#新聞広告を參照。
都市の景観に関する問題
1990年代後半より(北海道の10萬人単位規模の地方都市では既に1980年代初頭から)、特に地方都市の繁華街中心部や駅前などの一等地に出店する消費者金融業者が増え、どの街に行っても大手業者の巨大な看板が占拠する事態が発生し続けている。これらによって、それぞれの街の持つ獨自の景観が破壊され、畫一的で沒個性的な街並みがつくられる原因のひとつとなっているという批判がある。いわゆるサラ金ビルも參照されたし。
宇野治所屬委員會
外務委員會委員
國際テロリズムの防止及び我が國の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員會委員
宇野治所屬團體
禁煙推進議員連盟
金融サービス制度を検討する會
自民黨トラック輸送振興議員連盟
速やかな政策実現を求める有志議員の會
日韓議員連盟